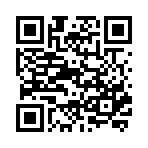2013年09月11日
佐藤賢一「新徴組」
「戊辰戦争に不敗伝説を残した、もうひとつの新撰組」という惹句に目を取られてしまったこの作品。
いつもは西洋史を舞台にした小説を書いている作者が、故郷である鶴岡の歴史にまつわる物語を書いたわけだが、史実に沿った出来事を盛り込もうとしたあまり主人公の活躍がイマイチな感じに終わってしまったのが残念。
森鴎外の残したテーゼ「歴史そのままと歴史離れ」を思い起こした。
いつもは西洋史を舞台にした小説を書いている作者が、故郷である鶴岡の歴史にまつわる物語を書いたわけだが、史実に沿った出来事を盛り込もうとしたあまり主人公の活躍がイマイチな感じに終わってしまったのが残念。
森鴎外の残したテーゼ「歴史そのままと歴史離れ」を思い起こした。
2012年10月03日
9月の読書
2012年07月16日
伊藤計劃「ハーモニー」
読んで良かった。
そう心から思える作品。
文章に込められた思慮の一つ一つに心を揺さぶられてしまった。
WatchMeと呼ばれる管理システムと体内に注入された医療分子によって完全に健康管理された無病の未来社会を舞台にしたこの作品。医療技術の目指すユートピアには違いないのだが、人間個々の精神的な発達から見るととんでもないディストピアに描かれている。
WatchMeで管理される個人個人の命はすべて社会のために使われるべきであって不健康な行動は反社会的な行為と見なされるようなリソース意識をみんなが持ち、そのため個人の持つ情報はすべてオープンにされ、プライヴァシーとは隠微なものに成り代わってしまった未来。
生活のすべては社会貢献のために行われていて、個人の自由を主張することが困難な世界。
作者の言葉によると「人間の持っている感情とか思考とかっていうものが、生物としての進化の産物でしかないっていう認識までいったところから見えてくるもの。その次の言葉があるのかどうか、っていうあたりを探っている。」ということらしいのだが、アリストテレスの言う「人間は社会的動物である」から、さらに先を突き詰めているのがこの作品だ。
動物としての人間と社会を構成する一員としての人間の二面に注目し、社会にその焦点を絞っていくと、完璧な社会システムが実現した世界においては人間の意識は必要ない、なんてこんな恐ろしいロジックを組みあがってしまうのだ。
正直に言うと、この内容には戦慄した。
これでは人間個々の考えを活かした社会など出来るわけがない。
また、そうとは思いつつも自分自身の中にも同様の解答が浮かび上がるのを感じた。
結末について書くことは控えるが、この作品に出会えたことに非常に感謝している。
しかし、同時に落胆もする。
この作者がもうこの世にいないということに、途方ものないつまらなさを感じる。
この次に作者が描くのがどんな未来だったのか、想像力の無さに涙しながら読み終えた。
そう心から思える作品。
文章に込められた思慮の一つ一つに心を揺さぶられてしまった。
WatchMeと呼ばれる管理システムと体内に注入された医療分子によって完全に健康管理された無病の未来社会を舞台にしたこの作品。医療技術の目指すユートピアには違いないのだが、人間個々の精神的な発達から見るととんでもないディストピアに描かれている。
WatchMeで管理される個人個人の命はすべて社会のために使われるべきであって不健康な行動は反社会的な行為と見なされるようなリソース意識をみんなが持ち、そのため個人の持つ情報はすべてオープンにされ、プライヴァシーとは隠微なものに成り代わってしまった未来。
生活のすべては社会貢献のために行われていて、個人の自由を主張することが困難な世界。
作者の言葉によると「人間の持っている感情とか思考とかっていうものが、生物としての進化の産物でしかないっていう認識までいったところから見えてくるもの。その次の言葉があるのかどうか、っていうあたりを探っている。」ということらしいのだが、アリストテレスの言う「人間は社会的動物である」から、さらに先を突き詰めているのがこの作品だ。
動物としての人間と社会を構成する一員としての人間の二面に注目し、社会にその焦点を絞っていくと、完璧な社会システムが実現した世界においては人間の意識は必要ない、なんてこんな恐ろしいロジックを組みあがってしまうのだ。
正直に言うと、この内容には戦慄した。
これでは人間個々の考えを活かした社会など出来るわけがない。
また、そうとは思いつつも自分自身の中にも同様の解答が浮かび上がるのを感じた。
結末について書くことは控えるが、この作品に出会えたことに非常に感謝している。
しかし、同時に落胆もする。
この作者がもうこの世にいないということに、途方ものないつまらなさを感じる。
この次に作者が描くのがどんな未来だったのか、想像力の無さに涙しながら読み終えた。
2012年05月20日
グレッグ・イーガン「プランク・ダイヴ」
文字通り世界最高のSF作家グレッグ・イーガン。
これには誰も口をはさむ余地は無いだろう。
日本で発売されている短編集「祈りの海」、「しあわせの理由」、「ひとりっ子」では、ハードなSFガジェットや数学理論を駆使しながら、人間の根源的心理を深くえぐるような作品が綺羅星のように並んでいる。
ハードな設定が多く難解さが読み手のハードルを上げているのだけど、分からないところは適度に読み飛ばすくらいがちょうどいい。
この短編集でも最初から飛ばしている。
仮想空間内における進化のシミュレーションに対する神のごとき関与は倫理に反するかという“クリスタルの夜”、自分のクローンを延命処置に利用する“エキストラ”、異性間コミュニケーションを描く“グローリー”などなど。
でも、一番気に入ったのは“ワンの絨毯”。
人間が知覚しているからこそ宇宙が存在するという人間宇宙論者が、肉体を捨てて自己をソフトウェア化して旅した宇宙の涯で初めて出会った異生物が、生物的コンピューター内に構築された仮想空間の生物だった、というエスプリの効いた作品。
自らを仮想化して見つけたのが仮想生物だったなんて、皮肉がたっぷりで笑ってしまった。
それから、最後の一編“伝播”
未完成の理由、それが分かればいい。
もしかしたら、これまでに見つかっている古代文明の謎もそのあたりで解けるのかもしれない。
未来へ伝えたいメッセージでもある。
これには誰も口をはさむ余地は無いだろう。
日本で発売されている短編集「祈りの海」、「しあわせの理由」、「ひとりっ子」では、ハードなSFガジェットや数学理論を駆使しながら、人間の根源的心理を深くえぐるような作品が綺羅星のように並んでいる。
ハードな設定が多く難解さが読み手のハードルを上げているのだけど、分からないところは適度に読み飛ばすくらいがちょうどいい。
この短編集でも最初から飛ばしている。
仮想空間内における進化のシミュレーションに対する神のごとき関与は倫理に反するかという“クリスタルの夜”、自分のクローンを延命処置に利用する“エキストラ”、異性間コミュニケーションを描く“グローリー”などなど。
でも、一番気に入ったのは“ワンの絨毯”。
人間が知覚しているからこそ宇宙が存在するという人間宇宙論者が、肉体を捨てて自己をソフトウェア化して旅した宇宙の涯で初めて出会った異生物が、生物的コンピューター内に構築された仮想空間の生物だった、というエスプリの効いた作品。
自らを仮想化して見つけたのが仮想生物だったなんて、皮肉がたっぷりで笑ってしまった。
それから、最後の一編“伝播”
未完成の理由、それが分かればいい。
もしかしたら、これまでに見つかっている古代文明の謎もそのあたりで解けるのかもしれない。
未来へ伝えたいメッセージでもある。
2012年05月16日
ゲイル・キャリガー「アレクシア女史、飛行船で人狼城を訪う」
英国パラソル奇譚の第二弾。
倫敦に拡がる異界族の力を奪う謎の病。
その解決方法を探るため、原因と思われるスコットランドへ主人公達は向かう。
そこで明らかになる夫の過去。
そして、父の事。
前作はぜんぜんスチームパンクじゃなかったけど、今作はエーテルグラフと呼ばれる無線連絡装置や飛行船、仕込みパラソルなどが登場し、ちょっとずつその片鱗を見せている。
ソウルレスこと反異界族の力も少しずつ明らかになっている。
“反異界族はつねに火葬される”
むずがゆかった一作目に比べるとはるかに面白い。
倫敦に拡がる異界族の力を奪う謎の病。
その解決方法を探るため、原因と思われるスコットランドへ主人公達は向かう。
そこで明らかになる夫の過去。
そして、父の事。
前作はぜんぜんスチームパンクじゃなかったけど、今作はエーテルグラフと呼ばれる無線連絡装置や飛行船、仕込みパラソルなどが登場し、ちょっとずつその片鱗を見せている。
ソウルレスこと反異界族の力も少しずつ明らかになっている。
“反異界族はつねに火葬される”
むずがゆかった一作目に比べるとはるかに面白い。
2012年05月01日
三島浩司「シオンシステム」
なんて幅広い小説なんだろう。
かぐや姫を大きなモチーフに据えながら、寄生虫による免疫力向上、寄生の系逆転、鳩の血統、厚生官僚、存在事実の喪失、還るべき場所とさまざまなテーマを持ちかけてくる。
それぞれが撚りあわさり物語が進んでいく。
複雑さに飽くこともなく、それでいて美しさを感じさせる。
次々と物語を進める人間は変わっていく。
それぞれ、一つの終息に向かっていく。
今現在どんどんと拡大を続けている宇宙が、いずれ収縮していくという説明を聞いたことがある。
そんな宇宙の定理と同じように進んでいくのが美しいのだろうか。
寄生虫をネタにした話を考えたことがある。
“食料不足に陥った未来(一種のデストピア)で、人類は体内に寄生虫を住まわせてセルロースを分解する酵素を手に入れる。しかし、寄生虫を手に入れられるのはまだほんの一握りの人間だけで、その卵を求めて争いが続いている。”
ある種の寄生虫を体内に飼っている人間は花粉症にならないという藤田紘一郎氏の著作にあった話を元に考えたネタだ。
今、花粉症になってしまった自分には寄生虫がいないことが分かった。デストピアも本当は嫌いだと感じている。
デストピアを描く作品が増えることは科学の発展にとって好ましくない、と言うようなことをグレッグ・イーガンが言っていたらしい。
僕自身もハッピーエンドを求めている。
かぐや姫を大きなモチーフに据えながら、寄生虫による免疫力向上、寄生の系逆転、鳩の血統、厚生官僚、存在事実の喪失、還るべき場所とさまざまなテーマを持ちかけてくる。
それぞれが撚りあわさり物語が進んでいく。
複雑さに飽くこともなく、それでいて美しさを感じさせる。
次々と物語を進める人間は変わっていく。
それぞれ、一つの終息に向かっていく。
今現在どんどんと拡大を続けている宇宙が、いずれ収縮していくという説明を聞いたことがある。
そんな宇宙の定理と同じように進んでいくのが美しいのだろうか。
寄生虫をネタにした話を考えたことがある。
“食料不足に陥った未来(一種のデストピア)で、人類は体内に寄生虫を住まわせてセルロースを分解する酵素を手に入れる。しかし、寄生虫を手に入れられるのはまだほんの一握りの人間だけで、その卵を求めて争いが続いている。”
ある種の寄生虫を体内に飼っている人間は花粉症にならないという藤田紘一郎氏の著作にあった話を元に考えたネタだ。
今、花粉症になってしまった自分には寄生虫がいないことが分かった。デストピアも本当は嫌いだと感じている。
デストピアを描く作品が増えることは科学の発展にとって好ましくない、と言うようなことをグレッグ・イーガンが言っていたらしい。
僕自身もハッピーエンドを求めている。
2012年04月02日
ゲイル・キャリガー「アレクシア女史、倫敦で吸血鬼と戦う」
ネオ・スチームパンクの謳い文句で書店に並んでいたこの小説。
でも、ぜんぜんスチームパンクじゃない。
そういうガジェットはほとんど登場しないから、スチームパンクを期待して読むとガッカリするかも。
これはヴィクトリア朝英国を舞台にしたゴシックホラーロマンスと言ってもいいかも。
人間と吸血鬼や人狼といった異界族とが共存する世界に、反異界族として生まれた主人公。まともな生活を過ごせるはずもなく、結婚適齢期を過ぎたオールドミスになり、家族に諦められながら今日も社交界へと顔を出す。
そこに登場するのがマコン卿。
スコットランド生まれの粗野な人狼ではあるが、ウルージ城人狼団のボスで社会的地位のある男。
はぐれ吸血鬼や人狼の失踪事件を追ううちに二人の距離は近づいていくという寸法だ。
しかし、ヴィクトリア朝の道徳観に沿うアレクシアと雌が主導権を握る人狼のしきたりに従うマコン卿が70年代の少女漫画みたいにかみ合わない。
“こんなに好きなのについ意地悪してしまう”的なノリで展開が行ったり来たりするので、読んでる方はやきもきさせられる。
後半はややエロくなるので割愛する。
女性らしい表現ではある。
最後に二人は結ばれるのだ。
さて、肝心なのはここから。
この作品の中で異界族と呼ばれる吸血鬼や人狼がどのように描かれているか。
この作品の歴史としては、まず古典的なホラーの描く世界と同じように人間と異界族がお互いに狩りあう<暗黒時代>があり、その後、異界族の存在が明らかになり、両者が認め合う形で同じ社会を形成しているのが作中の現在である。
異界族は自らの血族と異界族になることを望む人間の従者たちによって吸血群や人狼団と呼ばれるグループを形成し、誰彼かまわず人間を襲うことはしない。もし、そのような事件が起これば秘密操作組織である異界管理局がその事件を取り締まる。
このように吸血鬼が血の繋がりを基にしたグループを築いているところは、アン・ライスのヴァンパイアクロニクルにも描かれている。親子関係がはっきりしていてそれによって権力の差が生まれているのだ。(それをぶっ壊したのが我らがレスタト。吸血鬼のくせにロックンローラーとしてデビューしてしまう跳ねっ返り)。
そして、虚実織り交ぜながら吸血鬼が歴史の表舞台に登場するところは「ドラキュラ紀元」から始まるキム・ニューマンの三部作にすでに描かれているところである。(ただし、こちらは歴史上の人物のほか、小説や映画に描かれた歴史上(?)の架空人物までもがこれでもかと登場するという山田風太郎の明治もの的な作品。)
ブラム・ストーカーの「ドラキュラ」を始めとする初期のホラー作品群では、吸血鬼や人狼に反社会的な性格を持たせていたのに、近年ではこういった傾向が全く見られないのは興味深いことだ。
また、作者が生み出した反異界族という存在がこの作品の肝である。
人間の天敵である異界族、そのさらに天敵となるのがこの反異界族。
反異界族の別名は魂なき者(ソウルレス)。
その身体に触れた異界族は全ての力を失い、人間と同じ状態になる。
太陽に身をさらすことができないはずの吸血鬼が、反異界族の主人公と手を繋ぎながら夕日を見る場面は非常に美しく感じた。
おそらく、この設定が物語の結末に絡むのだろう。
人間と異界族と反異界族、どんな未来が待っているのか楽しみ。
でも、ロマンスがしつこかったので、星は三つだけ。
でも、ぜんぜんスチームパンクじゃない。
そういうガジェットはほとんど登場しないから、スチームパンクを期待して読むとガッカリするかも。
これはヴィクトリア朝英国を舞台にしたゴシックホラーロマンスと言ってもいいかも。
人間と吸血鬼や人狼といった異界族とが共存する世界に、反異界族として生まれた主人公。まともな生活を過ごせるはずもなく、結婚適齢期を過ぎたオールドミスになり、家族に諦められながら今日も社交界へと顔を出す。
そこに登場するのがマコン卿。
スコットランド生まれの粗野な人狼ではあるが、ウルージ城人狼団のボスで社会的地位のある男。
はぐれ吸血鬼や人狼の失踪事件を追ううちに二人の距離は近づいていくという寸法だ。
しかし、ヴィクトリア朝の道徳観に沿うアレクシアと雌が主導権を握る人狼のしきたりに従うマコン卿が70年代の少女漫画みたいにかみ合わない。
“こんなに好きなのについ意地悪してしまう”的なノリで展開が行ったり来たりするので、読んでる方はやきもきさせられる。
後半はややエロくなるので割愛する。
女性らしい表現ではある。
最後に二人は結ばれるのだ。
さて、肝心なのはここから。
この作品の中で異界族と呼ばれる吸血鬼や人狼がどのように描かれているか。
この作品の歴史としては、まず古典的なホラーの描く世界と同じように人間と異界族がお互いに狩りあう<暗黒時代>があり、その後、異界族の存在が明らかになり、両者が認め合う形で同じ社会を形成しているのが作中の現在である。
異界族は自らの血族と異界族になることを望む人間の従者たちによって吸血群や人狼団と呼ばれるグループを形成し、誰彼かまわず人間を襲うことはしない。もし、そのような事件が起これば秘密操作組織である異界管理局がその事件を取り締まる。
このように吸血鬼が血の繋がりを基にしたグループを築いているところは、アン・ライスのヴァンパイアクロニクルにも描かれている。親子関係がはっきりしていてそれによって権力の差が生まれているのだ。(それをぶっ壊したのが我らがレスタト。吸血鬼のくせにロックンローラーとしてデビューしてしまう跳ねっ返り)。
そして、虚実織り交ぜながら吸血鬼が歴史の表舞台に登場するところは「ドラキュラ紀元」から始まるキム・ニューマンの三部作にすでに描かれているところである。(ただし、こちらは歴史上の人物のほか、小説や映画に描かれた歴史上(?)の架空人物までもがこれでもかと登場するという山田風太郎の明治もの的な作品。)
ブラム・ストーカーの「ドラキュラ」を始めとする初期のホラー作品群では、吸血鬼や人狼に反社会的な性格を持たせていたのに、近年ではこういった傾向が全く見られないのは興味深いことだ。
また、作者が生み出した反異界族という存在がこの作品の肝である。
人間の天敵である異界族、そのさらに天敵となるのがこの反異界族。
反異界族の別名は魂なき者(ソウルレス)。
その身体に触れた異界族は全ての力を失い、人間と同じ状態になる。
太陽に身をさらすことができないはずの吸血鬼が、反異界族の主人公と手を繋ぎながら夕日を見る場面は非常に美しく感じた。
おそらく、この設定が物語の結末に絡むのだろう。
人間と異界族と反異界族、どんな未来が待っているのか楽しみ。
でも、ロマンスがしつこかったので、星は三つだけ。
2012年03月17日
ウェスタ—フィールド「リヴァイアサン」
第一次世界大戦を舞台にしたスチームパンクの第一作。
スチームパンクというと、蒸気機関が発達した世界でガチャガチャと歯車で動くガジェットが暴れまわるイメージで、小説ではギブスン&スターリングの「デファレンス・エンジン」、アニメでは「スチームボーイ」や「怪傑蒸気探偵団」などを思い出す。
この作品も例に漏れず、蒸気機関を動力とする機械技術の発達した国々(「クランカー」)が登場。スターウォーズに出てくるAT-ATみたいな多脚式歩行機械が走り回る。その用途は乗用から戦闘用までさまざまで、ドレットノート級なんて名前が付けられているあたり軍事マニアをニヤッとさせる。
しかし、普通のスチームパンクとちょっと違うところが一つある。
クランカーの対抗勢力として、遺伝子改良技術が発達したダーウィニストと呼ばれる国も登場することだ。名前のとおりダーウィンの唱えた進化論を基礎とした生物学の発展した勢力で、遺伝子操作で人工的に生み出した生物を使役している。
当然のことながら、クランカーとダーウィニストは対立している。蒸気機関発祥の地イギリスがダーウィニストという設定には異を唱えたいところだが、この対立の構図を第一次世界大戦の国際情勢とリンクさせているから致し方ない。
さて、表題の「リヴァイアサン」は、言わずと知れた旧約聖書に登場する海の怪物だが、この作品ではダーウィニストに生み出された巨大飛行船の名前とされている。
飛行船と言ってもヒンデンブルクやグラーフ・ツェッペリンのようなものではなく、空飛ぶ巨大なクジラのイメージ。体内を歩く描写もあるけど、それはさすがに気持ち悪い。
この世界に登場するのがおぼっちゃま育ちで世間ずれしたハプスブルク家公子アレックと、男装の英国空軍士官候補生デリン。この二人がスイスで出会い、リヴァイアサンに乗って冒険の旅に出発するまでが第一作めのストーリー。
様々な失敗を繰り返しながらも即座に状況を理解するアレックの賢さと女性でありながらも周囲の男性に負けない果敢さを見せるデリンの勇気が特徴付けられた本作。次第に信頼しあっていく二人の次作以降での活躍が楽しみ。
baraking spiders!
※ポケットブック版は味があっていいのだけど、1,600円は高いように感じる。
スチームパンクというと、蒸気機関が発達した世界でガチャガチャと歯車で動くガジェットが暴れまわるイメージで、小説ではギブスン&スターリングの「デファレンス・エンジン」、アニメでは「スチームボーイ」や「怪傑蒸気探偵団」などを思い出す。
この作品も例に漏れず、蒸気機関を動力とする機械技術の発達した国々(「クランカー」)が登場。スターウォーズに出てくるAT-ATみたいな多脚式歩行機械が走り回る。その用途は乗用から戦闘用までさまざまで、ドレットノート級なんて名前が付けられているあたり軍事マニアをニヤッとさせる。
しかし、普通のスチームパンクとちょっと違うところが一つある。
クランカーの対抗勢力として、遺伝子改良技術が発達したダーウィニストと呼ばれる国も登場することだ。名前のとおりダーウィンの唱えた進化論を基礎とした生物学の発展した勢力で、遺伝子操作で人工的に生み出した生物を使役している。
当然のことながら、クランカーとダーウィニストは対立している。蒸気機関発祥の地イギリスがダーウィニストという設定には異を唱えたいところだが、この対立の構図を第一次世界大戦の国際情勢とリンクさせているから致し方ない。
さて、表題の「リヴァイアサン」は、言わずと知れた旧約聖書に登場する海の怪物だが、この作品ではダーウィニストに生み出された巨大飛行船の名前とされている。
飛行船と言ってもヒンデンブルクやグラーフ・ツェッペリンのようなものではなく、空飛ぶ巨大なクジラのイメージ。体内を歩く描写もあるけど、それはさすがに気持ち悪い。
この世界に登場するのがおぼっちゃま育ちで世間ずれしたハプスブルク家公子アレックと、男装の英国空軍士官候補生デリン。この二人がスイスで出会い、リヴァイアサンに乗って冒険の旅に出発するまでが第一作めのストーリー。
様々な失敗を繰り返しながらも即座に状況を理解するアレックの賢さと女性でありながらも周囲の男性に負けない果敢さを見せるデリンの勇気が特徴付けられた本作。次第に信頼しあっていく二人の次作以降での活躍が楽しみ。
baraking spiders!
※ポケットブック版は味があっていいのだけど、1,600円は高いように感じる。
2012年03月06日
久保俊治「羆撃ち」
胸にズシッとのしかかるような読後感。
スーパーで食材を買って食べているような生活の中では決して味わえない死と向き合う感覚を重く感じた。
人間は生物である。
生物であるから、他の生物を補食し、自らの糧として生きる。
生きている限りは、常に他の生物の死に包まれている。
しかし、店先に並ぶパッケージには調理しやすい大きさに切り分けられた肉や魚が当たり前のように陳列され、忌避するように死の存在は隠されている。
まるで無機物のように。
違う。
これは違う、と感じる。
本当の生は、死に囲まれている。
本文の中で作者は言う。
“自然の中で生きた者は、すべて死をもって、生きていたときの価値と意味を発揮できるのではないだろうか。”
この世に生まれ出でた者は、死ぬことで、生きていた意味を成す。それは連綿と続いてきた生命の歴史そのものを表す。
“斃された獲物が、生きてきた価値と意味を充分以上に発揮するように、すべてを自分の内に取り入れてやる。自分の生きる糧とするのだ。”
だからこそ、ハンターとして斃した獲物の全てを、余すところなく売る、食べる。
人間は良くも悪くも、社会という一つの枠組みの中で多くの家畜を殺し、食材としている。
そして、なかには食べられることなく廃棄されるものもいる。
それが無性に哀しい。
生きることと死ぬことは同義である。
そんな思いを再確認した。
スーパーで食材を買って食べているような生活の中では決して味わえない死と向き合う感覚を重く感じた。
人間は生物である。
生物であるから、他の生物を補食し、自らの糧として生きる。
生きている限りは、常に他の生物の死に包まれている。
しかし、店先に並ぶパッケージには調理しやすい大きさに切り分けられた肉や魚が当たり前のように陳列され、忌避するように死の存在は隠されている。
まるで無機物のように。
違う。
これは違う、と感じる。
本当の生は、死に囲まれている。
本文の中で作者は言う。
“自然の中で生きた者は、すべて死をもって、生きていたときの価値と意味を発揮できるのではないだろうか。”
この世に生まれ出でた者は、死ぬことで、生きていた意味を成す。それは連綿と続いてきた生命の歴史そのものを表す。
“斃された獲物が、生きてきた価値と意味を充分以上に発揮するように、すべてを自分の内に取り入れてやる。自分の生きる糧とするのだ。”
だからこそ、ハンターとして斃した獲物の全てを、余すところなく売る、食べる。
人間は良くも悪くも、社会という一つの枠組みの中で多くの家畜を殺し、食材としている。
そして、なかには食べられることなく廃棄されるものもいる。
それが無性に哀しい。
生きることと死ぬことは同義である。
そんな思いを再確認した。
2012年01月23日
逢坂剛「猿曳遁兵衛 重蔵始末(三)」
幕末の北方調査で知られる近藤重蔵の若き日を描いたシリーズ。
北海道開拓史をひもとくと必ず目にする名前だが、どのような人物かはほとんど知らないので、先入観なしに読むことができる。
しかも、幕末の三蔵の一人に数え上げられるほどの俊英であるから、つまらないわけがない。火盗改方の与力として、若輩ながらも一を聞いて三を知るような深い洞察力と果敢な行動力によって、次々と事件を解決していく。
周りを固める人物も話に深みを加える。
配下の橋場余一郎、根岸団平、馴染みの鰻屋「はりま」の主人為吉と妻おえん、南奉行所の小物くちなわの弥七、そして悪党の一味であるおりよなど多彩。
歴史的な背景をしっかり記述するあたりは、作者のスペインものの手法を思い出させる。
今巻の中では、為吉とおえんを軸に据えた「盤石の無念」が一番面白かった。
次巻からは長崎編へとうつるみたいだ。
非常に楽しみ。
北海道開拓史をひもとくと必ず目にする名前だが、どのような人物かはほとんど知らないので、先入観なしに読むことができる。
しかも、幕末の三蔵の一人に数え上げられるほどの俊英であるから、つまらないわけがない。火盗改方の与力として、若輩ながらも一を聞いて三を知るような深い洞察力と果敢な行動力によって、次々と事件を解決していく。
周りを固める人物も話に深みを加える。
配下の橋場余一郎、根岸団平、馴染みの鰻屋「はりま」の主人為吉と妻おえん、南奉行所の小物くちなわの弥七、そして悪党の一味であるおりよなど多彩。
歴史的な背景をしっかり記述するあたりは、作者のスペインものの手法を思い出させる。
今巻の中では、為吉とおえんを軸に据えた「盤石の無念」が一番面白かった。
次巻からは長崎編へとうつるみたいだ。
非常に楽しみ。
2012年01月23日
東直己「ボーイズ・ビィ・アンビシャス」
ススキノハーフボイルド第2作。
大学生になった松井省吾はなぜか北大じゃなく、道央学院国際グローバル大学(通称:グロ大)に通っていた。
前作同様、とまどいの連続。
周りの見えない若造が主人公ということもあり、話の裏を読むのに苦労する。
しかも、事件の原因には歴史的経緯が絡んでおり、まともにミステリを読む感覚ではない。エルロイのノワール的な流れ。北海道選出の疑惑のデパート的議員がモチーフになっている。
便利屋やアンジェラなど作者お馴染みの面子が出てくるのでシリーズものとしては充分楽しめる。便利屋の冗長すぎる会話も面白い。が、単体としてはちょっと疑問符。
文庫化されたってことは、続編の話があるのかな?
大学生になった松井省吾はなぜか北大じゃなく、道央学院国際グローバル大学(通称:グロ大)に通っていた。
前作同様、とまどいの連続。
周りの見えない若造が主人公ということもあり、話の裏を読むのに苦労する。
しかも、事件の原因には歴史的経緯が絡んでおり、まともにミステリを読む感覚ではない。エルロイのノワール的な流れ。北海道選出の疑惑のデパート的議員がモチーフになっている。
便利屋やアンジェラなど作者お馴染みの面子が出てくるのでシリーズものとしては充分楽しめる。便利屋の冗長すぎる会話も面白い。が、単体としてはちょっと疑問符。
文庫化されたってことは、続編の話があるのかな?
2012年01月16日
半村良「闇の中の哄笑」
嘘部シリーズ三部作の最終作にして最高傑作。
嘘部一族は、嘘をつくことで日本の歴史を闇で操り続けてきた、ってのが前作までの嘘だったのだが、今作になったら結局のところ人間はみんな嘘つきだ、ってところまで立派に昇華されてしまっている。
笑った。
そして、これには全く恐れ入った。
実際、誰もが正直で隠しごともなく過ごす世界など想像できない。
多かれ少なかれ皆嘘をついて生きているのだ。
それを分かった上で生きていられるかどうか。
慣用表現ではなく真実として“清濁併せ飲む”行為を自らに受け入れさせられることが時には必要だろう。
作家の作った物語に乗せられているとは思いつつも、なんとも共感してしまった作品。
嘘部一族は、嘘をつくことで日本の歴史を闇で操り続けてきた、ってのが前作までの嘘だったのだが、今作になったら結局のところ人間はみんな嘘つきだ、ってところまで立派に昇華されてしまっている。
笑った。
そして、これには全く恐れ入った。
実際、誰もが正直で隠しごともなく過ごす世界など想像できない。
多かれ少なかれ皆嘘をついて生きているのだ。
それを分かった上で生きていられるかどうか。
慣用表現ではなく真実として“清濁併せ飲む”行為を自らに受け入れさせられることが時には必要だろう。
作家の作った物語に乗せられているとは思いつつも、なんとも共感してしまった作品。
2011年12月20日
中島敦全集
何度も何度も読み返している僕の最もお気に入りの本。
高校の国語の教科書で「山月記」を読んだのが最初だった。もうそれから、文章のリズムにどっぷりと浸かっている。
「隴西の李徴は博学才穎、天保の末年、若くして名を虎傍に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃むところすこぶる厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかった。」
この出だしを音読するだけでけっこうテンションが上がる。
漢文の素養がなければ、生み出されないこの文章。言葉と音の運びが美しい。
もちろん、他の掲載作も素晴らしいものばかり。
「名人伝」も「李陵」も変な言い方をすれば、現代の長さだけが頼りの小説とは違い、一つ一つの言葉が頭を切り裂くように入り込んでくる。
そして、白眉は「悟浄出世」と「悟浄嘆異」。
西遊記から沙悟浄を選ぶという着眼点もすごいが、師を求めて様々な妖怪を訪れる姿を諸子百家が並び立つ古代中国に重ね合わせて縦横無尽に生を語らせているその内容が特に惹かれる。
納得できない難しがりやは、きっと自分の中にもいるんだろう。
「フン、フン、どうも、うまく納得が行かぬ。」
この沙悟浄のセリフに自分を重ねてしまう。
それで、ついついまた読み返してしまうんだ。
高校の国語の教科書で「山月記」を読んだのが最初だった。もうそれから、文章のリズムにどっぷりと浸かっている。
「隴西の李徴は博学才穎、天保の末年、若くして名を虎傍に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃むところすこぶる厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかった。」
この出だしを音読するだけでけっこうテンションが上がる。
漢文の素養がなければ、生み出されないこの文章。言葉と音の運びが美しい。
もちろん、他の掲載作も素晴らしいものばかり。
「名人伝」も「李陵」も変な言い方をすれば、現代の長さだけが頼りの小説とは違い、一つ一つの言葉が頭を切り裂くように入り込んでくる。
そして、白眉は「悟浄出世」と「悟浄嘆異」。
西遊記から沙悟浄を選ぶという着眼点もすごいが、師を求めて様々な妖怪を訪れる姿を諸子百家が並び立つ古代中国に重ね合わせて縦横無尽に生を語らせているその内容が特に惹かれる。
納得できない難しがりやは、きっと自分の中にもいるんだろう。
「フン、フン、どうも、うまく納得が行かぬ。」
この沙悟浄のセリフに自分を重ねてしまう。
それで、ついついまた読み返してしまうんだ。
2011年10月12日
心に残る一言
ブクログの機能に、読み終わった本からの引用というものがある。
気に入った文面を残しておける。
自分自身、レビューを書きながら、心に残る一文を入力している。
そんな中でも気に入った一文はこの作品から。
忍法さだめうつし (祥伝社文庫)
言わずと知れた変態伝奇作家荒山徹の作品。
この250ページにこんな一文がある。
「では、妖術に頼ろう」
普通の剣豪小説であれば、研鑽を積んで剣術で勝負をするところをあっさりと妖術に頼ってしまうあたりが荒山徹。
あまりにもおかしくて笑ってしまった。
この気持ち分かるだろうか?
気に入った文面を残しておける。
自分自身、レビューを書きながら、心に残る一文を入力している。
そんな中でも気に入った一文はこの作品から。
忍法さだめうつし (祥伝社文庫)
言わずと知れた変態伝奇作家荒山徹の作品。
この250ページにこんな一文がある。
「では、妖術に頼ろう」
普通の剣豪小説であれば、研鑽を積んで剣術で勝負をするところをあっさりと妖術に頼ってしまうあたりが荒山徹。
あまりにもおかしくて笑ってしまった。
この気持ち分かるだろうか?
2011年10月12日
東直己「半端者ーはんぱもんー」
ブクログで読書目標とか掲げてしまって、学生時分依頼の制約を持って読書に臨んでいる今日この頃です。
文庫カバーが一新されてからまた買い始めたこのシリーズを読んでいる。
文庫カバーが一新されてからまた買い始めたこのシリーズを読んでいる。
ススキノ便利屋シリーズの文庫書き下ろしの新刊にして、時系列的にはシリーズ中もっとも古い時代を扱った作品。
どんな苦境にあっても減らず口を叩き、社会の違和感に対して不愉快さを隠そうともしない不屈の便利屋の大学在学中の物語である。
前日譚というものは概して、多くの制約に縛られながら創られるものであるために、ダイナミックさに乏しくこぢんまりとした印象を受けるのであるが、この作品はなかなかうまく描けているのではないだろうか。
30年もの年月に渡って便利屋を続けることになる主人公が抱くススキノで働く者に対する思いの原点。関わると縁起が悪いとまで言われることになる桜庭との出会い、それから、桐原との出会い。そして、他の作品でも語られたフィリピーナの関わる事件。
時代背景もあるのだろうが、序盤は昭和軽薄体を意識したような文体で語られていく。若さ故の自己中心的な考えが見え隠れし、30代後半の己自身としては嗜めようとする気持ちが浮かんでくるんだが、それでいながら懐かしさを感じさせる青臭さも同時に見せてくれる。
また、前日譚でありながら、シリーズ初期では見られないくらいに窮地に陥る主人公。きっとこれがベースとなって、後々の不屈さ、減らず口に繋がっていくのだろう。
誰にでも青い時代はあるのだ。
そんな思いを起こさせる、そんな作品。
ミステリとしては目立ったところはない。
ハードボイルドとしては青臭い。
けれど、青春小説として心を揺さぶられた。
ぜんぜん関係ないが、いつからススキノ探偵シリーズになったのだろう?便利屋のはずだろ。
どんな苦境にあっても減らず口を叩き、社会の違和感に対して不愉快さを隠そうともしない不屈の便利屋の大学在学中の物語である。
前日譚というものは概して、多くの制約に縛られながら創られるものであるために、ダイナミックさに乏しくこぢんまりとした印象を受けるのであるが、この作品はなかなかうまく描けているのではないだろうか。
30年もの年月に渡って便利屋を続けることになる主人公が抱くススキノで働く者に対する思いの原点。関わると縁起が悪いとまで言われることになる桜庭との出会い、それから、桐原との出会い。そして、他の作品でも語られたフィリピーナの関わる事件。
時代背景もあるのだろうが、序盤は昭和軽薄体を意識したような文体で語られていく。若さ故の自己中心的な考えが見え隠れし、30代後半の己自身としては嗜めようとする気持ちが浮かんでくるんだが、それでいながら懐かしさを感じさせる青臭さも同時に見せてくれる。
また、前日譚でありながら、シリーズ初期では見られないくらいに窮地に陥る主人公。きっとこれがベースとなって、後々の不屈さ、減らず口に繋がっていくのだろう。
誰にでも青い時代はあるのだ。
そんな思いを起こさせる、そんな作品。
ミステリとしては目立ったところはない。
ハードボイルドとしては青臭い。
けれど、青春小説として心を揺さぶられた。
ぜんぜん関係ないが、いつからススキノ探偵シリーズになったのだろう?便利屋のはずだろ。
2011年09月15日
ススキノ探偵と集合体と写楽
ここんとこ読書づいてる。
ブクログに記録してるレビューもたまってきたのでここに載せておく。
久しぶりに感じたが、ありきたりでも何でもかまわないが俺の趣味は読書で間違いない。やっぱり好きなんだ。むしろ、最近は読書しない人も増えているから、「読書が趣味です」なんて言うのは希少種なのかもしれない。
そういやこの前、自己紹介の趣味の欄に「幽体離脱」って書いてる人と同席した。いい人なんだけど、大丈夫か?と心配になった。
ブクログに記録してるレビューもたまってきたのでここに載せておく。
久しぶりに感じたが、ありきたりでも何でもかまわないが俺の趣味は読書で間違いない。やっぱり好きなんだ。むしろ、最近は読書しない人も増えているから、「読書が趣味です」なんて言うのは希少種なのかもしれない。
そういやこの前、自己紹介の趣味の欄に「幽体離脱」って書いてる人と同席した。いい人なんだけど、大丈夫か?と心配になった。
誰にでも気の進まない仕事はある。
生活のためと我慢して、それを受け止めている。
しかし、まったく気の合わないやつと友達になれ、なんて仕事だったらどうだろうか?
毎晩酒に付き合って面白くもない話を続けるなんて、俺には無理だ。
そんな無茶な設定から始まるのがこの作品だ。
殺人の疑いのある精神的にちょっとイっちゃってる中年男との飲み屋での会話が描かれるのだが、その中年男の会話が思わず嫌悪感を感じてしまうくらいのひどさなので、そのあたりはけっこう辛い。作者の腕と言える。きっと酒場での実体験が多分に含まれているのだろう。
ミステリとして凝ったところはないけれども、殺人の証拠があると考えられる中年男の自宅に侵入するために四苦八苦するところが面白い。
まわりのキャラクターも相変わらず活き活きと動き回っている。群像劇として楽しめる。
シリーズ物ならではの作品と言えよう。
生活のためと我慢して、それを受け止めている。
しかし、まったく気の合わないやつと友達になれ、なんて仕事だったらどうだろうか?
毎晩酒に付き合って面白くもない話を続けるなんて、俺には無理だ。
そんな無茶な設定から始まるのがこの作品だ。
殺人の疑いのある精神的にちょっとイっちゃってる中年男との飲み屋での会話が描かれるのだが、その中年男の会話が思わず嫌悪感を感じてしまうくらいのひどさなので、そのあたりはけっこう辛い。作者の腕と言える。きっと酒場での実体験が多分に含まれているのだろう。
ミステリとして凝ったところはないけれども、殺人の証拠があると考えられる中年男の自宅に侵入するために四苦八苦するところが面白い。
まわりのキャラクターも相変わらず活き活きと動き回っている。群像劇として楽しめる。
シリーズ物ならではの作品と言えよう。
ススキノ便利屋シリーズ。
このシリーズの札幌はいくつもの闇に包まれていて、認知症介護、オレオレ詐欺、闇金、再開発利権など様々な問題が複層的に描かれていく。
おそらく作者自身は、北海道に生まれ育ち、その土地を愛しているに違いない。しかし、北海道警察不正問題がそんな作者の心を抉りとってしまった。初期衝動とも言える慟哭が、形を変えて小説になっているように感じる。
これまでにないくらい生命の危機にさらされる便利屋。それは作者自身のストレスなのかもしれない。
このシリーズの札幌はいくつもの闇に包まれていて、認知症介護、オレオレ詐欺、闇金、再開発利権など様々な問題が複層的に描かれていく。
おそらく作者自身は、北海道に生まれ育ち、その土地を愛しているに違いない。しかし、北海道警察不正問題がそんな作者の心を抉りとってしまった。初期衝動とも言える慟哭が、形を変えて小説になっているように感じる。
これまでにないくらい生命の危機にさらされる便利屋。それは作者自身のストレスなのかもしれない。
遺伝子工学により肉体を改変され、複数の人間でいながら一個体と活動することが出来る集合体。
このアイデアで真っ先に思い浮かぶのが、シオドア・スタージョンの「人間以上」に描かれたホモ・ゲシュタルトだろう。(超能力者の集団という意味では、筒井康隆「七瀬ふたたび」も近いものを感じる)
社会に適応できない超能力者たちが力を合わせることによって、大きな力を持つ一個体になる、というのがホモ・ゲシュタルトであり、日本の合体ロボのイメージが近似している。
しかし、この小説の中に描かれる集合体は、生まれる前から遺伝子工学により集合体として生きていくように設計された人間のグループであって、それぞれ交渉や計算、腕力などの各分野に特化して身体を作り替えられているため、一人一人では満足に作業をこなすことも出来ない。意志決定に際しては、集合体内で討議が行われ(情報は共有できる)、決定役が最終的に判断する。繋がりが途切れると混乱して行動を止めてしまう。一人一人名前を持ち、個性を有するが、集合体としての名前も持つ。
なんだかとてもバランスが悪いような気がするのだが、彼ら一人一人の個性が物語を楽しく魅せてくれる。思慮深かったり、臆病だったり、感情的だったり、それら全てが集合体として一人の中に収束していく。
一人よりも複数で考えて、よりよい答えを選んでいくという彼ら。結局は僕らの社会だって同じものを目指しているのだから、それを単純化しているだけにも思える。
アイデアは面白い。
あとは物語の必然性をもっと詰めてくれれば最高だった。
・メダ以前に誰もリングに入らなかったのは何故か?
・レトは他の誰にもインターフェイスをつけなかったのか?
・もっと多くのAIがあらわれない理由は?
・5人ポッドの必要性は?
このアイデアで真っ先に思い浮かぶのが、シオドア・スタージョンの「人間以上」に描かれたホモ・ゲシュタルトだろう。(超能力者の集団という意味では、筒井康隆「七瀬ふたたび」も近いものを感じる)
社会に適応できない超能力者たちが力を合わせることによって、大きな力を持つ一個体になる、というのがホモ・ゲシュタルトであり、日本の合体ロボのイメージが近似している。
しかし、この小説の中に描かれる集合体は、生まれる前から遺伝子工学により集合体として生きていくように設計された人間のグループであって、それぞれ交渉や計算、腕力などの各分野に特化して身体を作り替えられているため、一人一人では満足に作業をこなすことも出来ない。意志決定に際しては、集合体内で討議が行われ(情報は共有できる)、決定役が最終的に判断する。繋がりが途切れると混乱して行動を止めてしまう。一人一人名前を持ち、個性を有するが、集合体としての名前も持つ。
なんだかとてもバランスが悪いような気がするのだが、彼ら一人一人の個性が物語を楽しく魅せてくれる。思慮深かったり、臆病だったり、感情的だったり、それら全てが集合体として一人の中に収束していく。
一人よりも複数で考えて、よりよい答えを選んでいくという彼ら。結局は僕らの社会だって同じものを目指しているのだから、それを単純化しているだけにも思える。
アイデアは面白い。
あとは物語の必然性をもっと詰めてくれれば最高だった。
・メダ以前に誰もリングに入らなかったのは何故か?
・レトは他の誰にもインターフェイスをつけなかったのか?
・もっと多くのAIがあらわれない理由は?
・5人ポッドの必要性は?
「邪馬台国はどこですか?」から続くシリーズの第三作目。さすがに一作目の衝撃には遠く及ばないように感じた。そもそも前作までと雰囲気が全く違うのだ。
酒場で歴史上の謎について丁々発止とやり合うのが愉快なシリーズだったのに、そのやり合ってた二人が恋人同士になってしまい、緊張感が薄れたように感じた。
それに全体的なトーンが物悲しく感じられた。最後の章で太平洋戦争を取り扱い、戦争を繰り返す愚かさをやるせなく描いているせいもあるだろう。
さらには、日本語タミル起源説を持ち出してきたのが、心に引っかかっている。恥ずかしながら大学でチョムスキーの生成文法論をわずかながらに囓った身としては、音韻論では言語の系統を明らかにすることは出来ないと信じている。当の大野晋でさえも後にはクレオールタミル語説を提唱したのではなかっただろうか。
以上の難点はあるものの、基本的には歴史上の謎について想像を巡らすというのは楽しい行為に変わりない。写楽の由来が「しゃらくさい」とか喝采を送りたい。
作者にはまたチャレンジしてもらいたい。
酒場で歴史上の謎について丁々発止とやり合うのが愉快なシリーズだったのに、そのやり合ってた二人が恋人同士になってしまい、緊張感が薄れたように感じた。
それに全体的なトーンが物悲しく感じられた。最後の章で太平洋戦争を取り扱い、戦争を繰り返す愚かさをやるせなく描いているせいもあるだろう。
さらには、日本語タミル起源説を持ち出してきたのが、心に引っかかっている。恥ずかしながら大学でチョムスキーの生成文法論をわずかながらに囓った身としては、音韻論では言語の系統を明らかにすることは出来ないと信じている。当の大野晋でさえも後にはクレオールタミル語説を提唱したのではなかっただろうか。
以上の難点はあるものの、基本的には歴史上の謎について想像を巡らすというのは楽しい行為に変わりない。写楽の由来が「しゃらくさい」とか喝采を送りたい。
作者にはまたチャレンジしてもらいたい。
2011年09月05日
東直己「駆けてきた少女」
再読。
以前に読了したのをすっかり失念して文庫本を買ってしまった。
この作品を書いたあたりの東直己は北海道警察の不正問題に対して、かなりの憤りを抱えていた時期で、同じ事件に関わる物語を主人公を変えて、「熾火」「ススキノハーフボイルド」、そして「駆けてきた少女」と後押し三作品も仕上げている。
本作、「駆けてきた少女」では、相変わらずのススキノ便利屋を主人公にバラエティ豊かなバイプレーヤーを脇に従えて(たまに主役になるけど)、物語は進められて行く。
のっけから腹を刺される便利屋。
脂肪が邪魔して致命傷にならなかったことをネタに笑われながら犯人を探していくあたりが軸になって、居残正一郎の道警不正暴露レポート、去勢ショー、高校生の死亡事件などが次々と織り込まれていく。すごい構成力だと思う。
繰り出される会話は、北海道弁丸出しでダジャレを織り交ぜながら、たまに文学的な話題を口にするという、飲み屋での会話そのものみたいで愉快だ。
元道民としては、どうしても読んでしまうシリーズなのだ。
以前に読了したのをすっかり失念して文庫本を買ってしまった。
この作品を書いたあたりの東直己は北海道警察の不正問題に対して、かなりの憤りを抱えていた時期で、同じ事件に関わる物語を主人公を変えて、「熾火」「ススキノハーフボイルド」、そして「駆けてきた少女」と後押し三作品も仕上げている。
本作、「駆けてきた少女」では、相変わらずのススキノ便利屋を主人公にバラエティ豊かなバイプレーヤーを脇に従えて(たまに主役になるけど)、物語は進められて行く。
のっけから腹を刺される便利屋。
脂肪が邪魔して致命傷にならなかったことをネタに笑われながら犯人を探していくあたりが軸になって、居残正一郎の道警不正暴露レポート、去勢ショー、高校生の死亡事件などが次々と織り込まれていく。すごい構成力だと思う。
繰り出される会話は、北海道弁丸出しでダジャレを織り交ぜながら、たまに文学的な話題を口にするという、飲み屋での会話そのものみたいで愉快だ。
元道民としては、どうしても読んでしまうシリーズなのだ。