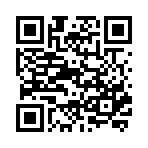2010年07月26日
永瀬隼介「ポリスマン」
エースではないが、確かな実力の持ち主。ひとたび道場破りや裏切り者が現れた時には、その強さで完膚なきまでに相手を叩きつぶす。
ポリスマンと言えば、そんなイメージを抱いていた。
藤原嘉明のように。
当然、この小説もポリスマン的な主人公が次々とトラブルを解決していく話だと思っていた。
けど、読み終わった今、そんなのは牧歌的な幻想に過ぎないと知ってしまった。
国を食い物にしつつ勢力拡大するロシアンマフィア、エンターテインメントの岐路にたたされたプロレス、血のつながらない家族、強さを手に入れた代償、隠された過去。
次々と現れる登場人物は一癖も二癖もあるやつばかり。
結末は残念だったけど、スピード感のある良い小説でした。
2010年07月17日
石井光太「レンタルチャイルド」
アジアの各国における障害者の暮らしを辿る、というのが出発点だったという。しかし、インド取材の際に障害者の物乞いがあまりにも多いことに気づく。そして、物乞いの収益をあげるために手足を切り落としたり、目をつぶしたりするマフィアの存在を知る。さらには、女性の乞食に乳幼児を貸し出し、レンタル料を取るシステムさえもあった。
ルポではありながらも、本書では明確な問題提起はしていない。原因を探ることなく、事象面を追っているのだ。その課程は物語的でノンフィクションではないかと疑わせる。
しかし、自分の想像の範囲内だけでは世の中のすべてを理解することは出来ない。外在するものを自分の中に受け入れるためには、まず抵抗をなくすことだ。
本書は3部構成。2002年、2004年、2008年とムンバイを取材している。
3部すべてに登場する人物が二人いる。マノージとラジャである。
6年間における二人の生活の変化は非常に対照的だ。
マノージは筆者の通訳として登場する。幼い頃にマフィアに片目をつぶされた元浮浪児で、人々からさげすまれながら何とか生きている。英語が話せることと、その出自を請われ通訳となる。それが、2004年には廃品回収で生計をたてるようになり、2008年にはインドの経済発展の影響もあり工事現場で働く労働者となり、家も購入し結婚もした。
一方でラジャは、街でマフィアの庇護を受けない子供の物乞いたちのリーダーとして登場する。マフィアのような汚い大人にはなりたくないと強く吐き捨てながら、2004年には自ら青年マフィアの一員となり搾取する立場へと変針する。しかし、それもわずかのことで人間関係のミスで権威を失墜した彼は街を去る。2008年、郊外の駅で再会した彼は死体すらも生計に利用する人物となっていた。
おどろくほどの落差だ。
両者に共通するのはある種のプライド。自分の欲のために他人を傷つけない。マフィアのようにはならない。
だが、苛烈な環境は二人を全く別の道を進ませる。
さげすまれながらも耐えて自分の道を見つけたマノージと、生き延びるために自分をごまかしながら落ちていったラジャ。そうしなければ、野垂れ死ぬしかなかったのだ。
本書はこういった状況を淡々と綴っている。
弱い者がさらに弱い者から奪う、悲惨で重苦しい状況である。
そういった中でも目を引く部分はある。
自分さえ生き抜くのが精一杯というのに死にかけた友人を気遣う物乞いや、まったく血の繋がらない同士がつくりだした親子関係など、強く他人を求める、あるいは求められることを望む姿だ。
他人との依存関係によって精神的なバランスを取っているともとれるが、根源的な部分で人は信頼関係を望んでいるものと信じたい。
暗い気分の時に読むとさらにどん底に行ってしまうので、余裕がある時に読むことをおすすめする。
ルポではありながらも、本書では明確な問題提起はしていない。原因を探ることなく、事象面を追っているのだ。その課程は物語的でノンフィクションではないかと疑わせる。
しかし、自分の想像の範囲内だけでは世の中のすべてを理解することは出来ない。外在するものを自分の中に受け入れるためには、まず抵抗をなくすことだ。
本書は3部構成。2002年、2004年、2008年とムンバイを取材している。
3部すべてに登場する人物が二人いる。マノージとラジャである。
6年間における二人の生活の変化は非常に対照的だ。
マノージは筆者の通訳として登場する。幼い頃にマフィアに片目をつぶされた元浮浪児で、人々からさげすまれながら何とか生きている。英語が話せることと、その出自を請われ通訳となる。それが、2004年には廃品回収で生計をたてるようになり、2008年にはインドの経済発展の影響もあり工事現場で働く労働者となり、家も購入し結婚もした。
一方でラジャは、街でマフィアの庇護を受けない子供の物乞いたちのリーダーとして登場する。マフィアのような汚い大人にはなりたくないと強く吐き捨てながら、2004年には自ら青年マフィアの一員となり搾取する立場へと変針する。しかし、それもわずかのことで人間関係のミスで権威を失墜した彼は街を去る。2008年、郊外の駅で再会した彼は死体すらも生計に利用する人物となっていた。
おどろくほどの落差だ。
両者に共通するのはある種のプライド。自分の欲のために他人を傷つけない。マフィアのようにはならない。
だが、苛烈な環境は二人を全く別の道を進ませる。
さげすまれながらも耐えて自分の道を見つけたマノージと、生き延びるために自分をごまかしながら落ちていったラジャ。そうしなければ、野垂れ死ぬしかなかったのだ。
本書はこういった状況を淡々と綴っている。
弱い者がさらに弱い者から奪う、悲惨で重苦しい状況である。
そういった中でも目を引く部分はある。
自分さえ生き抜くのが精一杯というのに死にかけた友人を気遣う物乞いや、まったく血の繋がらない同士がつくりだした親子関係など、強く他人を求める、あるいは求められることを望む姿だ。
他人との依存関係によって精神的なバランスを取っているともとれるが、根源的な部分で人は信頼関係を望んでいるものと信じたい。
暗い気分の時に読むとさらにどん底に行ってしまうので、余裕がある時に読むことをおすすめする。
2010年07月07日
有川浩「海の底」
作者曰く自衛隊三部作の一つ、海上自衛隊の部らしい。
海中から押し寄せる甲殻類。
人間を食べるというあり得ない状況。
甲殻類パニック小説。
と思って読んでいたが、ちょっと中身は違う。
潜水艦の中に閉じ込められた自衛官二人と子供たちが主役だ。
子供同士の対立、子供と大人の対立、家族の構築、自立への道、さまざまなテーマが盛り込まれている。
読んでいるうちに分かった。
これは「中学生日記」なんだ。
あの番組で描かれているテーマが全部入ってるよ。
警察と自衛隊についても割とつっこんで書いてるけど、やはりメインは子供たちだろう。
閉鎖空間の中で子供たちがどう成長していくのか。
それが一番でかい。
自分が親としての目線で見てるからかなー。
海中から押し寄せる甲殻類。
人間を食べるというあり得ない状況。
甲殻類パニック小説。
と思って読んでいたが、ちょっと中身は違う。
潜水艦の中に閉じ込められた自衛官二人と子供たちが主役だ。
子供同士の対立、子供と大人の対立、家族の構築、自立への道、さまざまなテーマが盛り込まれている。
読んでいるうちに分かった。
これは「中学生日記」なんだ。
あの番組で描かれているテーマが全部入ってるよ。
警察と自衛隊についても割とつっこんで書いてるけど、やはりメインは子供たちだろう。
閉鎖空間の中で子供たちがどう成長していくのか。
それが一番でかい。
自分が親としての目線で見てるからかなー。
2010年07月01日
垣根涼介「ボーダー ヒートアイランド4」
ヒートアイランドシリーズの第4巻。
犯罪者として生きる道を進む主人公を描くこのシリーズも、ノワールになるのかと思えば登場人物がすべて悪人には見えないという弱点があるため、いまいちノワールになりきれない。
犯罪者を描きつつも、人間模様を楽しむのが一番いいようだ。
このシリーズは面白いとは思うが、甘い部分ばかりが目につくようなら無理に続けなくてもいいと思う。
最近、北野武の「アウトレイジ」を観てきたが、ノワールもあそこまで行くと笑うしか無くなる。「キル・ビル」もそうだった。首がスパーンと飛んでいくシーンで笑ってしまうのだ。
恐怖でも歓喜でも悲しみでも一定のラインを越えると、方向性は違っていても心を刺激するという面では同じなのだ。
俺は刺激を求めている。
犯罪者として生きる道を進む主人公を描くこのシリーズも、ノワールになるのかと思えば登場人物がすべて悪人には見えないという弱点があるため、いまいちノワールになりきれない。
犯罪者を描きつつも、人間模様を楽しむのが一番いいようだ。
このシリーズは面白いとは思うが、甘い部分ばかりが目につくようなら無理に続けなくてもいいと思う。
最近、北野武の「アウトレイジ」を観てきたが、ノワールもあそこまで行くと笑うしか無くなる。「キル・ビル」もそうだった。首がスパーンと飛んでいくシーンで笑ってしまうのだ。
恐怖でも歓喜でも悲しみでも一定のラインを越えると、方向性は違っていても心を刺激するという面では同じなのだ。
俺は刺激を求めている。