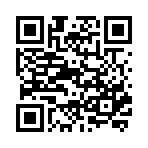2010年02月23日
山田風太郎「警視庁草紙」
いやあ、面白い。
カオスだね、カオス。
ごった煮の時代って何があるか分かんないから、史実と物語を混ぜても違和感ないってことだ。
うちの爺さんは明治末の生まれで、25年前に89才で亡くなった。
やたらと人に教えたがり、それで師匠面するような人だったそうだ。この近辺にはまだ導入されていなかった機械の操作を大阪に行ってまで覚え、それが各地に普及するのにあわせて指導して歩き、酒や料理をご馳走になっていい顔をしていたという。顔見知りの多い岩手県北だけではなく下北半島あたりまで行っていたというから、これもまた驚き。
まあ、何かというと明治気質というかある種の豪放さを備えた人物であったことは間違いないのだ。
さて、山田風太郎のこの連作集。西郷隆盛が東京を去る時から、西南戦争勃発までの期間を舞台としている。明治初めということもあり制度もまだまだ整備されておらず、維新の残り火も燻っている状態のなか、新たな保安機関として設置された警視庁が東京の治安維持に勤めようとするのを、旧幕府町奉行所の面々が足を引っ張るという楽しい内容。
元町奉行所の面々の体制に媚びず、という姿勢を貫く姿は意固地にも見えるが、実際自分が同じ立場になったらそうなるかもと感じさせるようなリアリティもある。
また、内容だけではなく登場人物も豪華絢爛。幕末の英雄やら、明治の元勲やら著名犯罪者やら講談の人物やら、まあここまでいくと魑魅魍魎としか感じられないが、斉藤一や今井信郎、清水の次郎長、森林太郎、三遊亭円朝、山田浅右衛門など名前が出てきただけでもワクワクす
る。
これらの人物と実際に起こった事件が複雑にコラージュされ、それがますます明治というカオスな時代を際だたせている。ホントかどうかは置いといて、物語として面白い。
これまで忍法帳だけ読んできたけどそれじゃダメなんだね。
明治物も読まなきゃ。
カオスだね、カオス。
ごった煮の時代って何があるか分かんないから、史実と物語を混ぜても違和感ないってことだ。
うちの爺さんは明治末の生まれで、25年前に89才で亡くなった。
やたらと人に教えたがり、それで師匠面するような人だったそうだ。この近辺にはまだ導入されていなかった機械の操作を大阪に行ってまで覚え、それが各地に普及するのにあわせて指導して歩き、酒や料理をご馳走になっていい顔をしていたという。顔見知りの多い岩手県北だけではなく下北半島あたりまで行っていたというから、これもまた驚き。
まあ、何かというと明治気質というかある種の豪放さを備えた人物であったことは間違いないのだ。
さて、山田風太郎のこの連作集。西郷隆盛が東京を去る時から、西南戦争勃発までの期間を舞台としている。明治初めということもあり制度もまだまだ整備されておらず、維新の残り火も燻っている状態のなか、新たな保安機関として設置された警視庁が東京の治安維持に勤めようとするのを、旧幕府町奉行所の面々が足を引っ張るという楽しい内容。
元町奉行所の面々の体制に媚びず、という姿勢を貫く姿は意固地にも見えるが、実際自分が同じ立場になったらそうなるかもと感じさせるようなリアリティもある。
また、内容だけではなく登場人物も豪華絢爛。幕末の英雄やら、明治の元勲やら著名犯罪者やら講談の人物やら、まあここまでいくと魑魅魍魎としか感じられないが、斉藤一や今井信郎、清水の次郎長、森林太郎、三遊亭円朝、山田浅右衛門など名前が出てきただけでもワクワクす
る。
これらの人物と実際に起こった事件が複雑にコラージュされ、それがますます明治というカオスな時代を際だたせている。ホントかどうかは置いといて、物語として面白い。
これまで忍法帳だけ読んできたけどそれじゃダメなんだね。
明治物も読まなきゃ。